小学校に入学すると、子育ても少し楽になった感じがします。
目が離せなかった子育てが終わり、教育を学校に依存してしまいがちです。
私は学童に預けていましたが、お迎えが最後になっていました。
でも、娘はいろいろなことを自分で学んでいたようです。
子育てを振り返り、こうすれば良かったことを、
子育て中の方と共有しようと思います。
- 小学校低学年の時に家庭教育で必要だと思うことを知りたい
- 子育て経験者の話を参考にしたい
- 今後、子育てをしていきたいが、考え方を知りたい
意志力、自立性を持つ子になるために
「〇〇しなさい」は子どもの意志力を弱くする
親は子どもの鏡
人は無意識のうちに周囲の影響を受けています。
・誰かが、ゴミを捨てると、ゴミを捨てる人が多くなる。
・友達が、バイトすると、自分もバイトしたくなる。
周囲の人が意志が弱く、ラクな方に流れてしまうと、その影響を受けやすくなります。
日常を共有している家族の影響は強いです。
子どもの意志力、自立性を成長させたければ、
家族も、意志力を持って行動していく、努力していくことが必要かもしれません。
子どもは自分で成長していく
好きなことを見つける「きっかけ」を作ってあげる
動機をつくってあげる
小学生の低学年くらいに好きになったことは、生涯の仕事になったり、趣味になったりします。
好きなことを見つける手助けをしてあげるのが、この頃に必要なことだと思います。
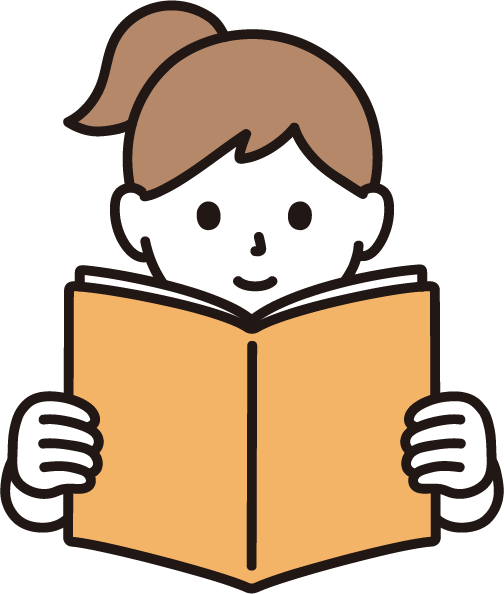
いろいろな体験をさせてあげる
親子の信頼関係をきずく
話をよく聞く
やる気を引き出す言葉
「どうする?」
人生は、選択の連続です。子どもの頃から選択の練習をしていく。
親が決めるのではなく、子供に選んでもらう機会を増やしていきましょう。
「わかるよ」「そうだね」
子どもが失敗した時や、悩んでいる時、いきなり怒られたら
「話を誰も聞いてくれない」と心を閉ざしてしまいます。
子どもが話を聞いてくれて、共感してくれるのは嬉しいと感じると、安心して、
間違いを改める勇気が生まれます。
「すごいね」
以前に80点のテストで90点になったら
「あと10点で100点だったね」と言ってしまうと親は頑張ったのに親は満足してくれないと
子どもはやる気を失ってしまいます。「10点も上がったんだね。すごいね」と
努力した過程をほめる。親が努力を褒めてくれたら
子どもは嬉しくてもっと頑張るようになります。

小学生低学年の7歳から9歳くらいは、好奇心がいっぱいで
なんでもやって見たい時だと思います。
この頃の体験は、人生の職業につながるような好きな物と
出会う時期なので、多くの体験をさせてあげ、
子どもの意志力や自立心を育ててあげたいですね。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日もほんわかハッピーに!
にほんブログ村


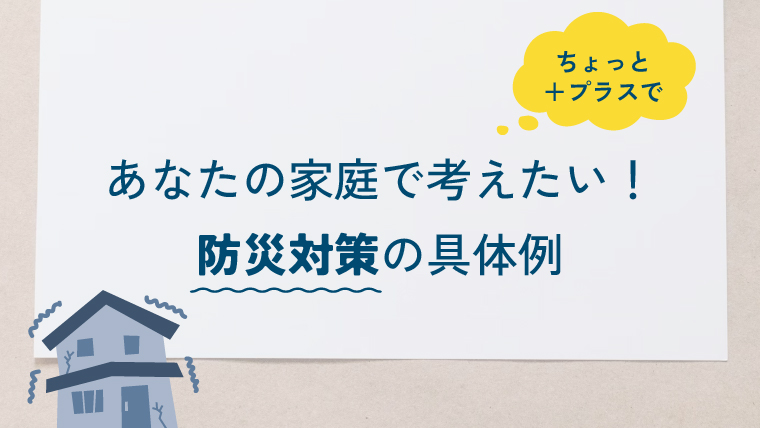

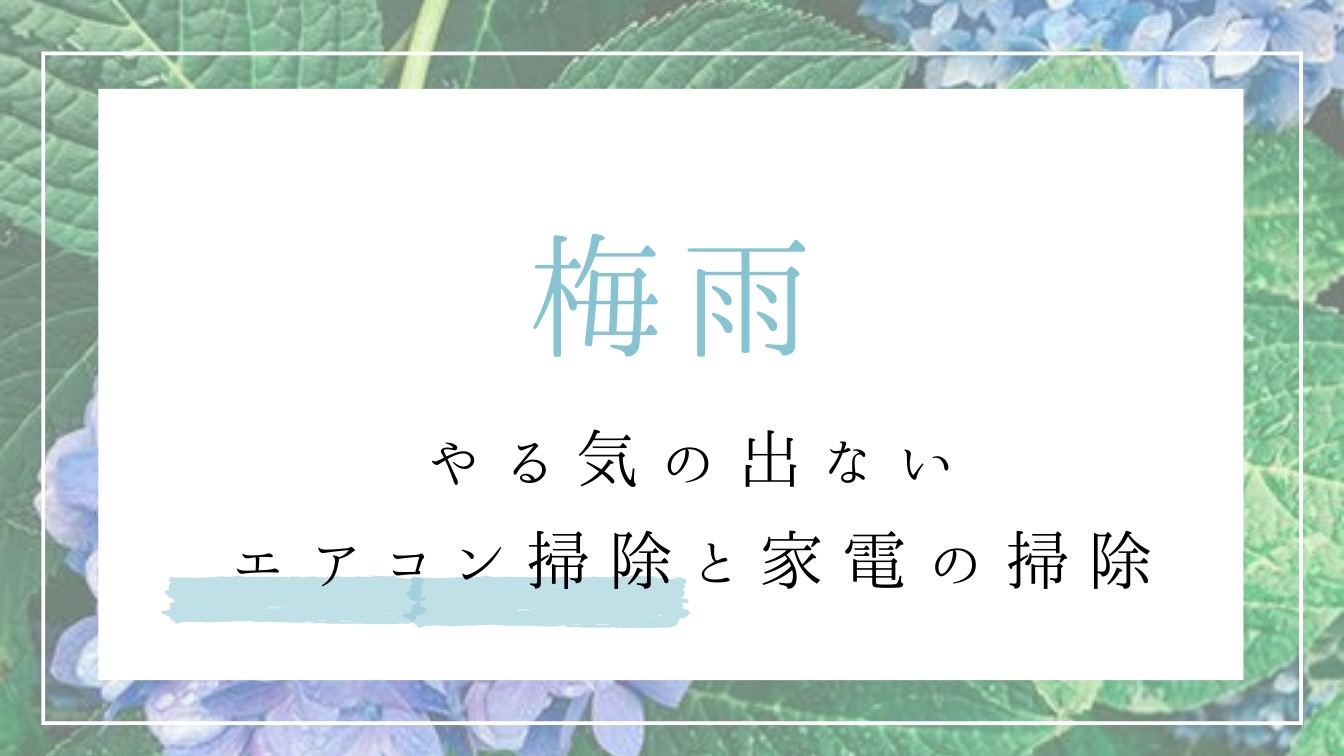

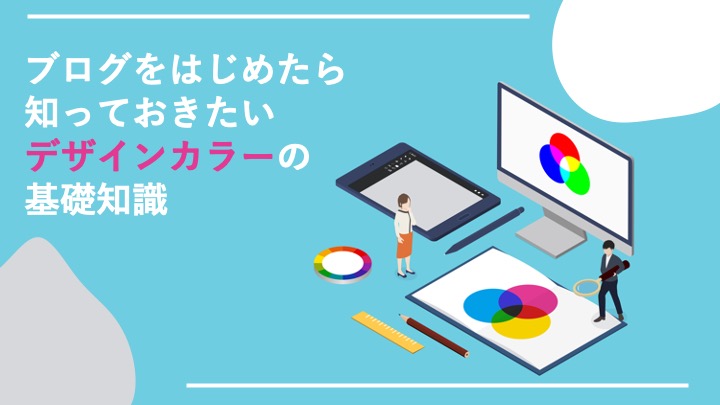
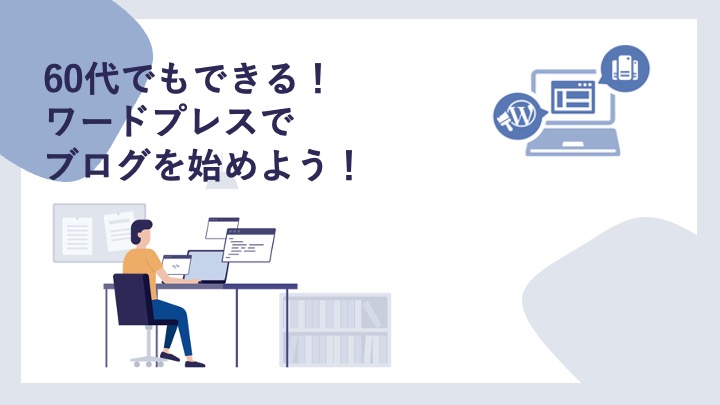
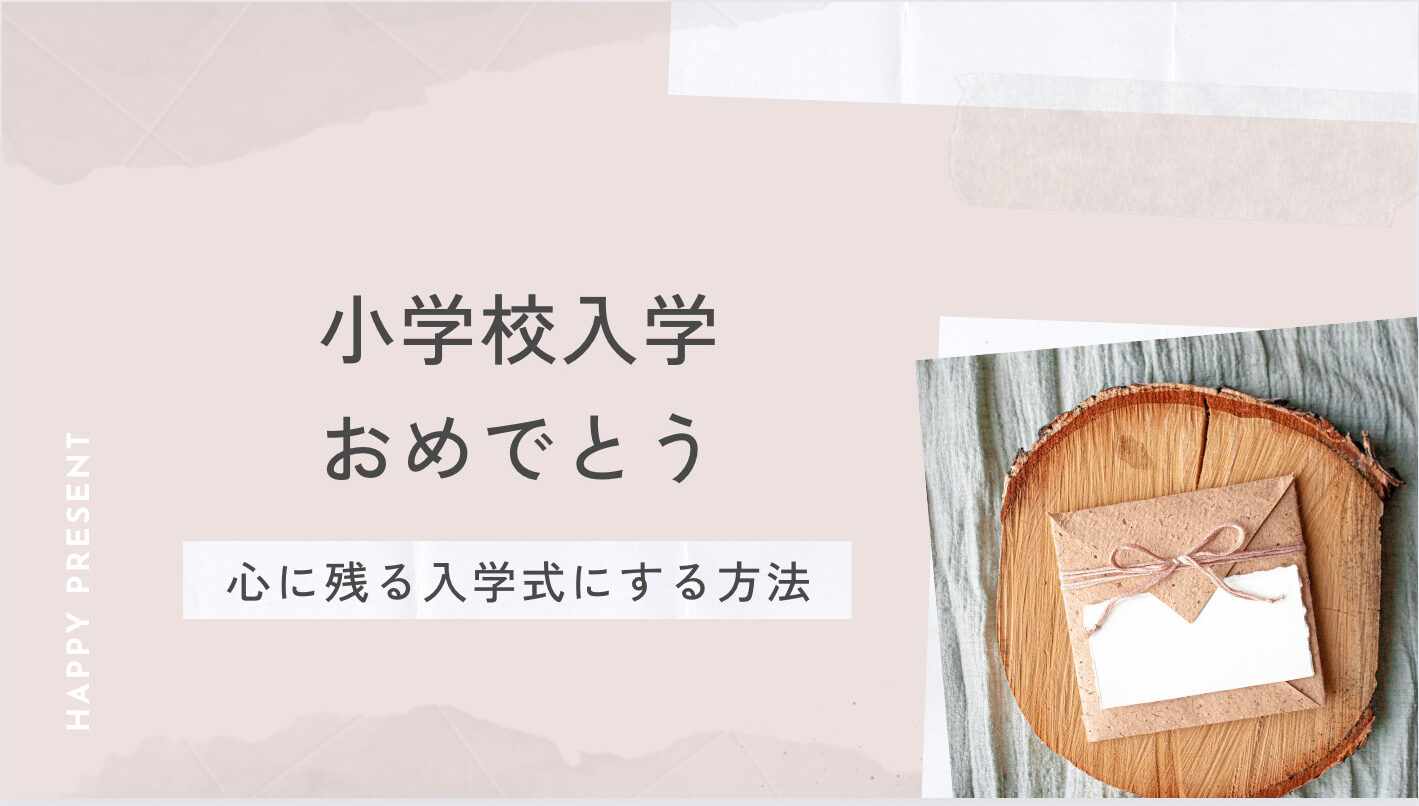

娘は、子どもの頃はマイペースで、時間があまり気にならない
感じでした。私は早くしたいタイプなので、
朝は通勤時間を気にしてしまいどうしても、せかしてしまう。
「早くしなさい」「これを着なさい」「早く食べなさい」
今、考えると「〇〇しなさい」は逆効果でした。